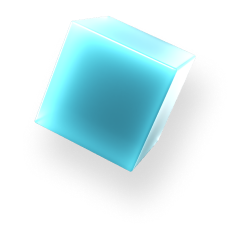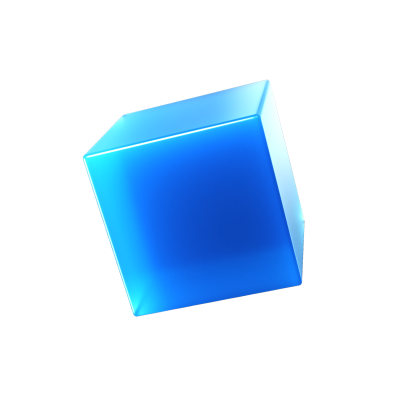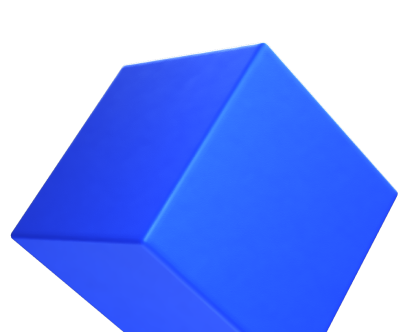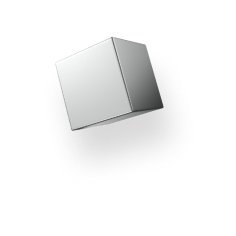技術と対話で、現場を変える生産技術職──世界一の先進工場を見据えた「想い」

ITのフル活用で、製造ラインでボトルネックを解決

北海道から九州まで全国の製造拠点でリレーやコネクタ、スイッチ類など、幅広い製品を生み出しているメカトロニクス事業部。生産技術職はそれらの工場で、IT活用によってより効率的な製造工程を実現する役割を担っている。伊藤にとって大きなきっかけとなったのは、パナソニックの現場を目の当たりにした、入社前のインターンシップだった。
入社から5年間で手掛けたのは、製造ラインのモノの流れと、そのデータをきれいに整える工程管理システムの開発だった。工場は「ここをよりよく変えられないか」といった課題感を抱き、伊藤ら生産技術のチームに力を貸してくれないかと声を掛ける。ターゲットとなるのは、工場で当たり前になっている、想定よりも時間がかかる業務だ。
2024年4月から、伊藤は新たな品質予測システムの構想を担当している。その狙いは一つの製品に使われている数々の部材、それらのデータと製品の仕上がりを数値化して、最適な材料を導くこと。従来であれば、現場のベテランならではの勘やコツに頼っていた微妙な感覚、そこを機械学習によって逆算する。
工場にとって一つの課題となっている「熟練の技術の継承」にも、伊藤らは正面から向き合っている。
現場とは一心同体で前進し、時に俯瞰で考える

自分の仕事で、最も大事なことは製造現場との関係性だと語る伊藤。まずは、現場でどこに課題感を持っているのか、ヒアリングが最初の入り口になる。同じ社内とはいえ、面識のない中で工場を訪れ、課題のコアを見いだすのは簡単ではない。
議論を重ね「このデータがポイント。もっと楽にスムーズにできる」と改善のメリットを示しながら、工場のメンバーとの信頼関係は厚みを増していく。しかし、そこで陥ってはいけないのが「ただ受け身で聞くばかりの存在」だと伊藤は語る。場合によっては数カ月間、一つの工場に通うこともあり、その中で自然と本音レベルの話ができるような関係性になってくる。建設的な議論が深まるにつれ、いつしか「ただ聞くだけの存在」になってしまう危うい面があるという。
一緒に歩みつつ、別の視点で製造ラインに臨む──。生産技術らしい信条がそこに垣間見える。
自分の理解を過信しない。恥を恐れず何度でも聞く

パナソニック インダストリーの特徴を問うと、伊藤は「チャレンジの風土」だと即答する。その理由は、最初にリーダーを任された2~3年目のプロジェクトで経験した挫折だった。
そこから学んだのは、恥を恐れずに何度でも聞くこと、自分の理解を相手に確認することです。ミスを引き起こした要因は、現場でヒアリングした内容を『こういうことだな』と思い込みでシステムをくみ上げたところにありました。聞いたことを自分の言葉に置き換え、次のステップに進む。そうした積み重ねが、現場を革新するチャレンジにつながります」
当時に受けた言葉を思い返すと、それは創業者の松下 幸之助から受け継がれている、人づくりの風土そのものだったと振り返る。
学生時代にはバックパック一つでさまざまな国を旅したり、バイクで東日本一周をしてみたりと、チャレンジ系の企画を好むタイプだったと自己分析をする伊藤。部署異動の希望を出して自身を生かせる社内制度などを例に挙げ、入社前に想像したとおり、あるいはそれ以上にパナソニック インダストリーは自分で考えてチャレンジできる領域が広いと、満面の笑みで語る。
見えないところから、見違える世界に変えていく

尊敬するエンジニアが間近にいる。
現場の声を聞く力、現場が気づいていない課題を見いだすスキル、さらにその先、未来を描いてどう近づけていくかをストーリーで語る……、その企画力に圧倒されるという。
いつか、かなえたいと思い描くのは「世界一の先進的な工場」をつくること。その一歩目は、目の前のお客様に役立つ技術を開発することに尽きると、大きな目標に向けた着実な積み重ねを結びつける。
世界に誇る日本のモノづくり、その競争力は衰えているかのようにも言われる。しかし、伊藤は「底力は決して負けていません」と胸を張る。IT活用が遅れている点に悔しさは感じながらも、だからこそAIや先進的な技術の開発と導入で、ガラッと日本の製造業は変わることができる、お客様にもさらに喜んでいただける商品を生み出せると、その自信は揺るぎない。
見えないところから、見違える世界に変えていく──そのために、自分自身も経験を重ねながら、もっと技術力とコミュニケーション力を高め、工場のメンバーと共に実現していきたいという熱い想いで、伊藤は今日も現場と向き合っている。
※ 記載内容は2024年7月時点のものです