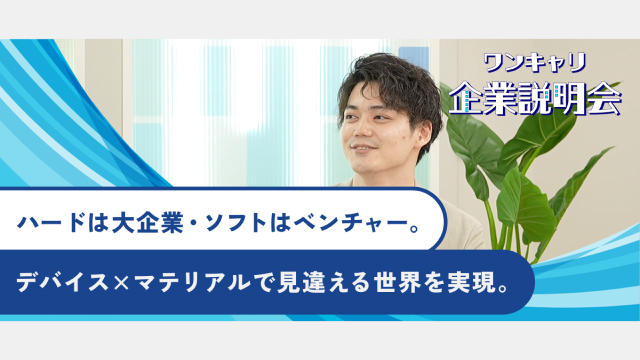転職者が語る“インダ”を選んだ「想い」──多彩なメンバーで創る、未来のパナソニック インダストリー

ホテル・飲料メーカー・外資系企業……さまざまなバックグランドからインダへ集結

──入社までのキャリアと転職のきっかけを教えてください。
音瀬 :
前職は大手鉄道グループのホテルカンパニーで、経営企画を担当していました。出身が京都ということもあり、親しみのあった観光業を志望していて、開発から手掛ける同社に魅力を感じて新卒で入社。フロントやレストランなど、一通りの業務を学んで、経営企画に異動しました。
経営に関わる資料をまとめる仕事をしていく中で、親会社・子会社という制約がある関係ではなく、一事業会社としてもっと自分たちで意思決定をして挑戦できる会社で働きたいと6年目で転職を考え始めました。
経営に関わる資料をまとめる仕事をしていく中で、親会社・子会社という制約がある関係ではなく、一事業会社としてもっと自分たちで意思決定をして挑戦できる会社で働きたいと6年目で転職を考え始めました。
岩永 :
これまで水処理業界や化学業界、飲料業界を経験し、業務に必要な資格を取得しつつ、生産設備のメンテナンスや日々の設備点検、給排水の分析業務などを担当しました。世界有数の飲料メーカーである3社目ではシーケンサーの制御変更や生産設備の定期オーバーホール業務も経験しました。
現場で経験を積み、そこで芽生えたのが「もっと大きく、俯瞰的な立場で仕事をしたい」という想いでした。これまでよりも目線を上げ、大規模なモノづくりで設備導入や更新計画にも関わっていきたいと思ったのが、転職のきっかけです。
現場で経験を積み、そこで芽生えたのが「もっと大きく、俯瞰的な立場で仕事をしたい」という想いでした。これまでよりも目線を上げ、大規模なモノづくりで設備導入や更新計画にも関わっていきたいと思ったのが、転職のきっかけです。
乙部 :
新卒時に選んだのは日本と海外の合弁企業の通信機器メーカーで、携帯電話のベースバンド設計として6機種を手掛けました。世界中の人々に使われ、生活に影響を与える製品のモノづくりに携われる喜びを感じました。
1度目の転職ではドイツの自動車部品メーカーで技術営業職として電気から機構まで幅広く担当。社会人としてスマホの誕生や電気自動車の普及というダイナミックな業界の移行期を経験しました。
トレンドの中心で働くことはやりがいが大きい半面、外資の自分が働けば働くほど日系メーカーのシェアを奪うことに葛藤を覚えていました。
1度目の転職ではドイツの自動車部品メーカーで技術営業職として電気から機構まで幅広く担当。社会人としてスマホの誕生や電気自動車の普及というダイナミックな業界の移行期を経験しました。
トレンドの中心で働くことはやりがいが大きい半面、外資の自分が働けば働くほど日系メーカーのシェアを奪うことに葛藤を覚えていました。
幅広くスケールが大きい事業領域、挑戦の社風が入社の決め手に

──中途採用市場はここ数年活況を迎えていて、転職先にはさまざまな選択肢があったかと思います。その中で、インダを選んだ「決め手」はどこにあったでしょうか?
音瀬 :
関西に本社機能を置く会社で絞り込んで転職先を探していた時に、環境の取り組みを社内外に伝える広報活動やエンゲージメント強化に特化したインダの募集が目に留まりました。GX戦略推進センターは新設部署で、ゼロからの立ち上げという挑戦に魅力を感じました。
実際に入社してみると、職場のメンバーも転入・転職の顔ぶれ。そのため、私たちの業務は何か1つ聞くにも「誰にコンタクトを取ればいいのだろう?」という人脈づくりから始まります。そうした一つひとつの課題にもチームで連携して動けていますし、入社前に描いた働き方ができています。
実際に入社してみると、職場のメンバーも転入・転職の顔ぶれ。そのため、私たちの業務は何か1つ聞くにも「誰にコンタクトを取ればいいのだろう?」という人脈づくりから始まります。そうした一つひとつの課題にもチームで連携して動けていますし、入社前に描いた働き方ができています。
岩永 :
私の場合は、設備の導入前から仕様調査や各種申請、保全業務に携わっていきたいという思いがありました。転職を考える中で、敷地の外からですがインダの工場を実際に見学したことで、働くイメージが湧いたのも大きなきっかけになりました。そこは事業部の中でも屈指の大きな工場で、製造ラインや設備のスケール感が私の思い描いていたイメージと一致しました。
また、これまでに経験した3社それぞれの待遇面や働く環境を見て、転職活動では並行して他社の面接も進んでいましたが、条件と働きがいが私のイメージに一番近い、この会社を選びました。
また、これまでに経験した3社それぞれの待遇面や働く環境を見て、転職活動では並行して他社の面接も進んでいましたが、条件と働きがいが私のイメージに一番近い、この会社を選びました。
乙部 :
入社の動機は「技術立国としての日本を子の世代、孫の世代に伝えたい」との想いから。スウェーデンに留学した学生時代、リトアニア出身の友人から「私の国の挨拶や料理を知っている?」と問われ言葉に詰まりました。「こんにちは」「寿司」と世界で知られているのは私たちより上の世代が日本のプレゼンスを高めたからだと思います。
プレゼンスを下げることなく次世代に引き継いでいくことに私も貢献したいと思い、次に転職する際は日本の技術や製品を世界へ届けることができる仕事をしようと考えました。
インダへの転職は世界に誇るパナソニックの技術力と開発力、国内で完結しない商習慣が決め手でした。入社してからは、想像した通りにカラフルな会社の印象を持っています。
プレゼンスを下げることなく次世代に引き継いでいくことに私も貢献したいと思い、次に転職する際は日本の技術や製品を世界へ届けることができる仕事をしようと考えました。
インダへの転職は世界に誇るパナソニックの技術力と開発力、国内で完結しない商習慣が決め手でした。入社してからは、想像した通りにカラフルな会社の印象を持っています。
──岩永さんから働く環境面での視点がありましたが、音瀬さんと乙部さんはいかがですか?
音瀬 :
公募型異動制度の存在は魅力的でした。「こういうことをやりたい!」と自ら手を挙げ、挑戦ができるという社風ということで好印象を持ちました。
乙部 :
私の所属先は虎ノ門にできる新拠点へオフィスを移転する予定と聞き、ミーハーですが都心のランドマーク的な新しいビルで働けることに心が躍りました(笑)。
あと、たまたま社長とエレベーターに同乗したことがあるのですが、とても新鮮でした。これまでの会社では社長をはじめとする重役は海外本社にいるものだったので。転職前には想定していませんでしたが、本社経営陣の働き方を身近で学ぶことができる環境も魅力的ですね。
あと、たまたま社長とエレベーターに同乗したことがあるのですが、とても新鮮でした。これまでの会社では社長をはじめとする重役は海外本社にいるものだったので。転職前には想定していませんでしたが、本社経営陣の働き方を身近で学ぶことができる環境も魅力的ですね。
入社すぐに加速する、キャリア入社の瞬発力

──入社して約1年半、現在はどんな業務を担っていますか?
音瀬 :
省エネや再エネなど、各拠点の環境の取り組みを社外に発信する広報的な役割を担っています。いかに技術の進化を環境の切り口で伝えるかがミッションです。Web媒体で施策や実績数値を紹介したり、CEATECなどの展示会で広くPRしたりと、社外向けの訴求でブランド価値の向上に努めています。
入社1年目から、思った以上にプロジェクトを主導する機会にも恵まれました。動画制作を手掛けたり、ホームページの刷新を担当したり、そこは良い意味で入社前に想像していた状況とはギャップがありました。
入社1年目から、思った以上にプロジェクトを主導する機会にも恵まれました。動画制作を手掛けたり、ホームページの刷新を担当したり、そこは良い意味で入社前に想像していた状況とはギャップがありました。
岩永 :
私は宇治拠点で設備更新・修理計画の策定や工事管理、消耗部品の発注、予実管理などの業務に就いています。東京ドームを超える敷地面積を誇る大規模工場で、蒸気やエアー、井水、純水、市水などのエネルギー使用量も他拠点と比較して多い拠点です。
長い歴史ある工場ですので、毎年、複数の設備更新があります。更新する設備に関して、その検討から立ち上げまで一貫して携われるところにやりがいを感じています。
工場の安定稼働を支えるためには、計画的整備と予防保全が欠かせません。これまでのキャリアで得た知見も活かしながら、工場全体を見渡しています。
長い歴史ある工場ですので、毎年、複数の設備更新があります。更新する設備に関して、その検討から立ち上げまで一貫して携われるところにやりがいを感じています。
工場の安定稼働を支えるためには、計画的整備と予防保全が欠かせません。これまでのキャリアで得た知見も活かしながら、工場全体を見渡しています。
乙部 :
営業本部に所属し、台湾市場に向けたマーケティングを担当しています。1つの商品群にとらわれず、広くパナソニックグループの商材を紹介する新規ビジネスです。すでに販路が確立された商材だけでなく、これまで海外で売ってこなかった製品や技術を紹介するのが私の役割。
たとえば、給湯器や暖房機器に使うポンプがAIサーバーの冷却機器に使えないかといった新しい展開を考え、事業部も想定していない用途で売っていく業務です。エンジニアから技術営業へ、そして海外マーケへ。これまでの経験を幅広く活かしながら働いていると実感します。
たとえば、給湯器や暖房機器に使うポンプがAIサーバーの冷却機器に使えないかといった新しい展開を考え、事業部も想定していない用途で売っていく業務です。エンジニアから技術営業へ、そして海外マーケへ。これまでの経験を幅広く活かしながら働いていると実感します。
見えないところから、見違える世界に変えていく

──キャリア入社者の視点から見て「インダのここは改善したい!」というポイントはありますか?
音瀬 :
これまでに感じてきたことの1つは、事業部ごとの高い独自運営性が生み出す複雑さです。自主責任経営を実施している半面、各部で規定やフローといったルールも異なるため、理解するのに時間を要しました。
乙部 :
音瀬さんと同じく、私も事業部間での連携が弱く、とくに情報が部署内で完結しがちと感じます。その壁を越えるため、自分の作った資料はなるべく多くの部署の方に発信するよう心がけています。インダの行動指針「共有から始めよう」の実践です。パナソニック内の固定観念にしばられることが少ないキャリア採用だからこそ風穴を開けられると思うので、これからも情報共有を促進していきたいですね。
岩永 :
特徴的だと思うのは当社には穏やかな方が多いこと。施設に関する専門知識はそれぞれにプロフェッショナルがいて、質問をすると手元の仕事を止めてでも親身に答えてくれます。
一方で気になっているのは、この道を究めている方が多いからこそ、社員個人の経験則に依存しがちな点。宇治工場は世代交代の真っ最中。過去の機器更新など、ノウハウを受け継ぐ仕組みには改善の余地があります。これまでに私が扱ったシステムで変えられる可能性もありますし、少しずつそうしたアップデートを進めていこうと考えています。
一方で気になっているのは、この道を究めている方が多いからこそ、社員個人の経験則に依存しがちな点。宇治工場は世代交代の真っ最中。過去の機器更新など、ノウハウを受け継ぐ仕組みには改善の余地があります。これまでに私が扱ったシステムで変えられる可能性もありますし、少しずつそうしたアップデートを進めていこうと考えています。
──今後に向けて、どんな「想い」を抱いていますか?
音瀬 :
「環境は費用がかかるし、ブランディングのための施策」といった先入観を持つ人も少なくありません。「環境貢献とは、経営と一体の活動である」というメッセージを、もっと社内外のステークホルダーに対して情報発信していきたい。私たちだからこそ組織横断の動きができます。
いろいろな人と交じり合い、環境価値と事業価値を結びつけられる関係性を築きたい。「環境に取り組む、パナソニック インダストリーの商品だから」と指名買いしていただけるような認知度の拡大をめざしています。
いろいろな人と交じり合い、環境価値と事業価値を結びつけられる関係性を築きたい。「環境に取り組む、パナソニック インダストリーの商品だから」と指名買いしていただけるような認知度の拡大をめざしています。
乙部 :
私は折々で自分のキャッチコピーを決めてキャリアを形成してきました。これまでは「自分が開発した製品を日本から世界へ」「グローバルスタンダード製品で、日本車を世界でより強く」。そして、今は「日本の技術や製品を世界へ」を掲げています。
海外に向けたマーケティング活動で、日本のモノづくりの未来に貢献したい。この想いも行動指針の1つ「世界を変えていく日々の仕事が、われわれの誇りだ」と一致します。いつか、海外赴任もできればと思っています。
海外に向けたマーケティング活動で、日本のモノづくりの未来に貢献したい。この想いも行動指針の1つ「世界を変えていく日々の仕事が、われわれの誇りだ」と一致します。いつか、海外赴任もできればと思っています。
岩永 :
私の目標はこの工場を永続的に保全していくこと。私自身が製品を直接生み出すわけではありませんが、工場の安定稼働を支える縁の下の力持ちとして支えていきたいと思います。
※ 記載内容は2025年1月時点のものです